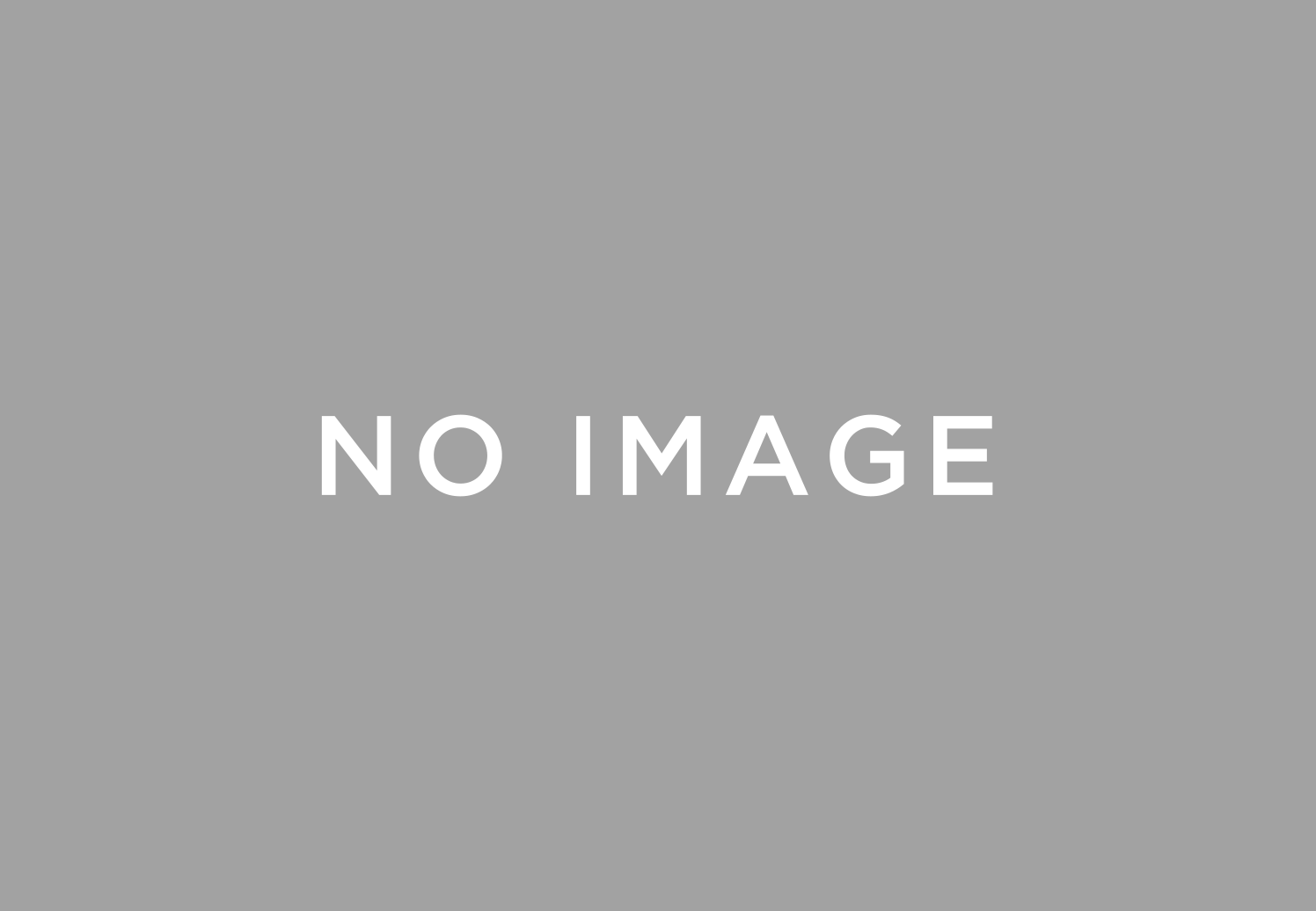公務員の係長昇任試験で、論文を書く時のコツ

僕は公務員の係長への昇任試験を受けるために、勉強中です。
現在、一次試験が終わり、二次試験を控えているところです。
二次試験の中には、論文があります。
職場の上司が昇任試験勉強会を主催してくれている中で、論文を書くコツが分かってきました。
そこで、係長昇任試験の論文執筆におけるコツを、書いておこうと思います。
今回は、地方自治法や地方公務員法ではなく、市政に対して問われる論文に関してです。
本市の場合は、文字制限が1000文字です。
そこに、論文の代表的な文章構成である
・起承転結 あるいは、
・序論・本論・結論
という段階に分けた場合、どのような文字数の配分が、バランスがいいでしょうか。
■起承転結の場合
・起 150文字
・承 350文字
・転 350文字
・結 150文字
■序論・本論・結論の場合
・序論 200文字
・本論 600文字
・結論 200文字
このくらいの文字数配分だと、全体的にバランスがよくみえます。
あくまでも目安なので、この数値に近づけるといいでしょう。
文字数だけではなく、執筆内容のバランスによっても、アピール度が違ってきます。
ここでも、「起承転結型」と「序論本論結論型」に分けて書き分けます。
■起承転結の場合
・起 社会情勢、市況、簡潔な結論
・承 テーマに挙げられた施策理解、キーワード
・転 自分の職場や経験における事例や具体策
・結 上記を踏まえた結論や係長としての覚悟
■序論・本論・結論の場合
・序論 社会情勢、市況、簡潔な結論
・本論 施策理解やキーワードを示しつつ、自分の職場や経験における事例や具体策をはさむ
・結論 上記を踏まえた結論や係長としての覚悟
最初に「簡潔な結論」を示すことで、読み手が最初から「このことについて書くんだな」と見通しがつきます。楽に頭に入るのです。
そして中盤で、「ちゃんと施策について理解してますよ、僕ならこうしますよ。」というアピールをします。具体性が大事です。
最後にはもう一度結論を書くことで、始めからの一貫した筋が通り、読み手に爽快感すら与えます。
しかも、施策理解や具体策まで踏まえてあるわけですから、「よく分かってるし、係長としてやっていけそうじゃないか。」などと思ってもらえるのです。
係長試験における論文テストは、社会批評を聞きたいわけではありません。
係長として、施策を踏まえながら、職場を運営していけるのか?
ここが問われているわけです。
だから、アピールすべきは、
「係長として、私はどうするのか?」
これです。
つい社会批評になりがちなところを、ぐいっと方向変換し、「係長として、こうしていきたいんだ!」という部分を念頭に書くようにしましょう。
論文は、係長としてどうしたいと思っているかが問われるので、必然的に面接試験にもつながります。
書きなれてない方も大勢いらっしゃると思いますが、面接試験にも、係長としての職場運営にも役立ちますので、しっかり論文の勉強時間を確保して、気合い入れていきましょう。