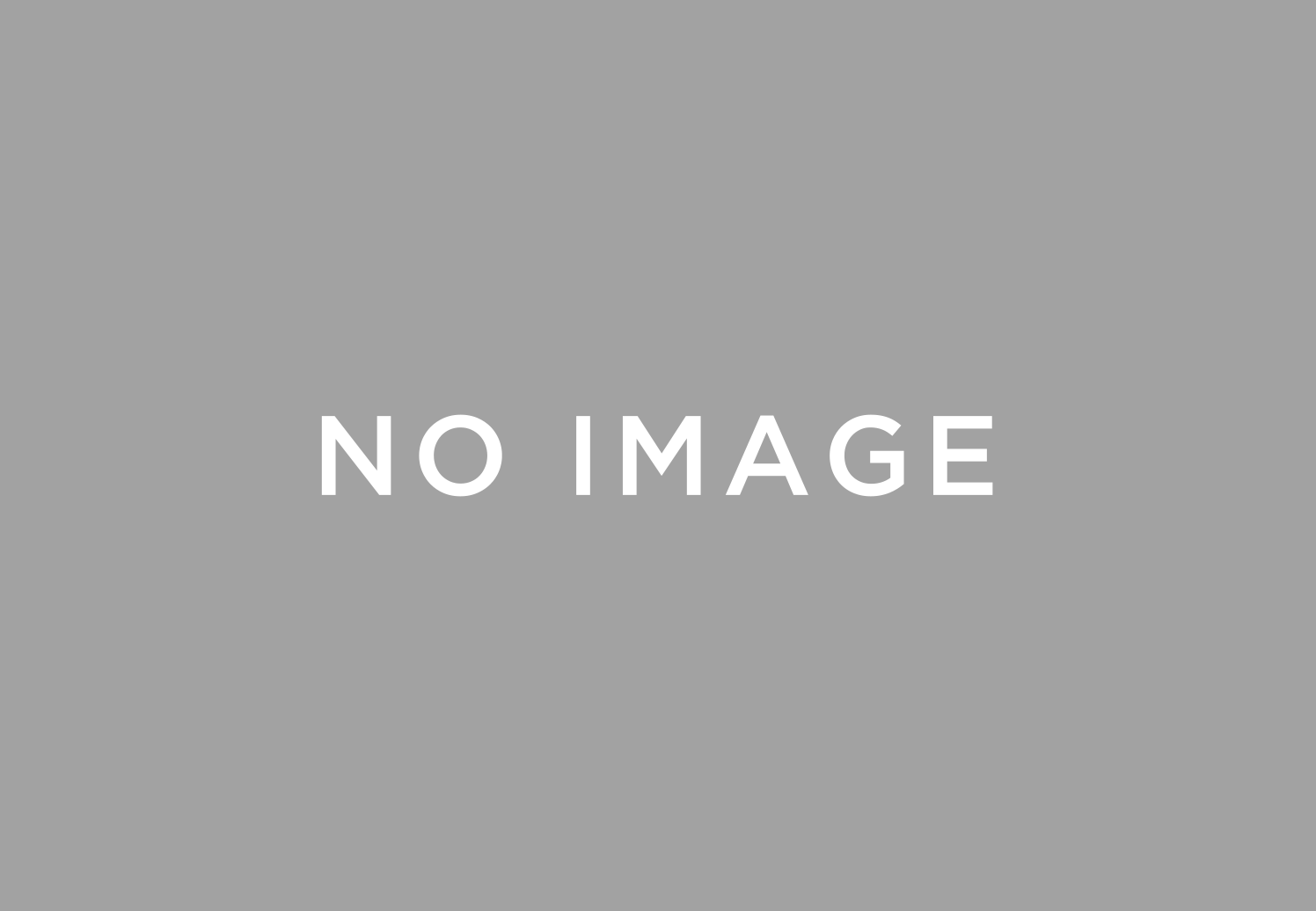行動を促すために、お菓子を使うのはダメなのか?【知的障害・自閉児支援】

知的障害や自閉の子の支援において、行動を促すために、お菓子を使うかどうかは、判断が分かれるところです。
というより、反対する人の方が圧倒的に多いでしょう。
「〇〇をしたら、お菓子をあげるからね。」
というかたちで、行動を促すのです。
なぜ反対されるかというと、
「お菓子のためにやっていることであって、習慣が身に付くわけではない。永遠にお菓子をあげつづけなきゃいけないのか。」
「おやつの時にお菓子をあげるのはいいとしても、それ以外の時間にお菓子をあげることで、食事に影響がでたりしないか。」
「いろんな場面で、お菓子を要求することになりはしないか。」
「専門的な支援とは、言葉がけや、環境整備によって課題を解決していくことであって、物で釣るのは専門家のやることではない。」
このような理由があるからです。
一方、「適切な行動を促したり、身に付けてもらうためには、お菓子などを利用しても構わない。」という考え方もあります。
「おいしいもののために、がんばるということは、誰だってよくあることじゃないか。」とも言われます。
事例
以前、僕の勤めていた施設でも、お菓子を使った事例がありました。
なかなかトイレに行くことができず、声掛けしても、定期的にトイレに連れて行っても、結局オムツに用を足してしまう子がいたのです。
そこで考えた職員が、
トイレで用を足せたら、お菓子をあげる
ということにしました。
小さいチョコレートがご褒美です。
するとその子は、だんだんとトイレで用を足すようになってきたのです。
そしてほとんどトイレで済ませることができるようになりました。
とりあえずは、計画の成功です。
実は、計画はそこにとどまりません。
ずっとお菓子をあげつづけるわけにはいかないという認識はあったので、次のステップへ進みました。
その子にとってのご褒美は、お菓子だけではありません。
職員とのコミュニケーション(抱っこや「いいこいいこ」すること)
もまた、大好きだったのです。
ですから、トイレで用を足せた時、お菓子をあげずに、大いにコミュニケーションをすることに移行していきました。
するとどうでしょう。お菓子がなくても、職員とコミュニケーションができるのがうれしくて、トイレに行くようになったのです。
最初は、「お菓子」というインパクトが必要でした。
嫌がる子に、「おしっこやうんちは、トイレでするものだ」という意識を持ってもらうには、強い動機が必要でした。
お菓子のためなら、トイレに行くか、と思ってもらうのです。
そして、トイレで用を足せば、褒められる。抱っこしてもらえる。という経験を毎日積むことで、やっとトイレに行く習慣が付いたのです。
「トイレに行くのも、悪くないな…」と、思ってくれたのかな。
これは、大成功でしたね。
なんでもかんでも、導入はお菓子というのは、もちろん間違っていると思います。
でも、ご褒美にお菓子を使うことを、全く検討もしない、という考え方も違うと思います。
その子にとって、ご褒美とは何なのか。
長期的にはどのように支援していくのか。
何が許せて、何が許せないのか。
そのように考えていく中で、お菓子も使いようだな~、と思ったのでした。